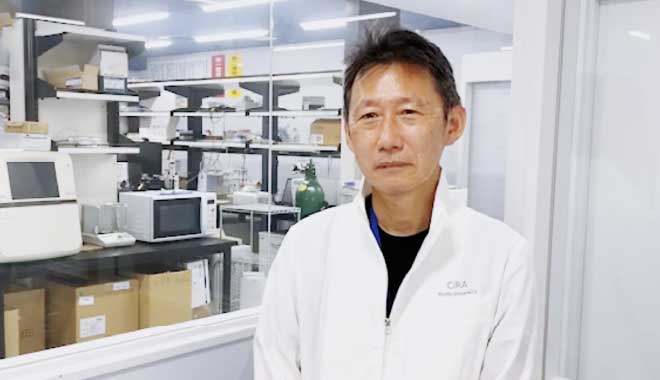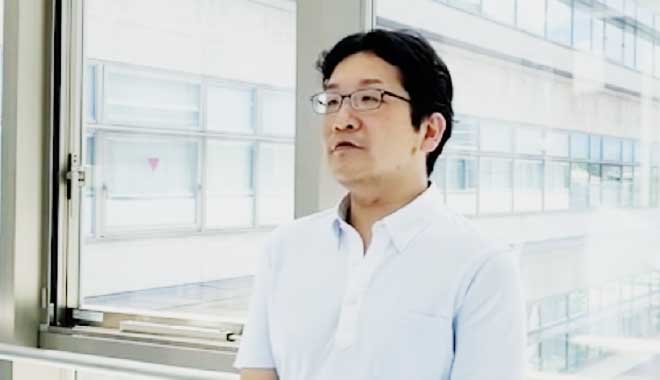臨床開発
大学で生まれたiPS細胞技術を産業界へ

公益財団法人京都大学iPS細胞研究財団

当財団は、国立大学法人京都大学iPS細胞研究所にあった一部の部門が分離し、2020年4月から公益財団法人として活動を開始しました。主な事業は、iPS細胞の製造・品質評価・提供で、大学と産業界の橋渡し役を務めています。
iPS細胞のように、大学で生まれた技術を実用化するには、その技術を大学から引き継いで、研究開発を進めてくれる企業が必要です。
しかし、新しい技術であるiPS細胞を使った再生医療の研究開発は、多くの時間とコストがかかり、企業にとっては、製造・販売にまで到達できないリスクが高い事業です。そのため、新規参入への一歩を踏み出せない企業も少なくありません。
当財団では、企業の参入障壁を少しでも減らせるように、iPS細胞の提供や細胞製造・細胞保管・品質評価などのサービスを、良心的な価格で提供しています。その中でも、当財団が提供しているiPS細胞ストック(*1)は、多くの日本人にとって拒絶反応が起きにくいことから、パーキンソン病や血小板減少症などの治験でも、移植用細胞の原料として使われています。
引き続き、他機関が進めているiPS細胞を使った再生医療の研究開発をサポートするとともに、独自の研究開発を進めることで、iPS細胞の実用化に貢献して参ります。
(*1)iPS細胞ストックとは、拒絶反応が起きにくい免疫型の組み合わせを有する健康なドナーから採取した血液からiPS細胞を作製し、あらかじめ様々な品質評価を行った上で、備蓄したiPS細胞のこと。iPS財団のiPS細胞ストックは、日本人で最も頻度の高い(第1位の)HLA型から第4位までを揃えていることから、日本人の約40%には拒絶反応が起こりにくいと考えられている。残りの60%の日本人および世界中の方にも使用できるように種類を揃えるには、莫大な費用と時間がかかるため、iPS財団ではゲノム編集技術を用いたiPS細胞の製造技術開発にも取り組んでいる。